「福利厚生としてオフィスおかんを検討してるんだけど、料金が高いという噂を聞いて導入を迷っている…」
「従業員は100円で利用できると聞くが、実際の会社の費用負担はどれくらいなのだろうか?」
こんな風に、オフィスおかんの料金体系に関して、具体的な費用感がわからず不安に感じている担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
たとえ従業員の満足度向上に繋がる魅力的なサービスであっても、コストが重すぎたらやはり導入は難しいものですよね。
この記事では、「オフィスおかんの料金は高い」という疑問に焦点を当て、その料金体系の仕組みから、会社負担の内訳、他社サービスとの比較まで、客観的な情報に基づいて詳しく解説します!
- オフィスおかんの料金体系(月額・会社負担)
- 「料金が高い」と感じる具体的な要因
- 他社サービスとの料金比較と相場観
- 費用対効果を踏まえた総合的な評価
オフィスおかんの料金は高い?その仕組みを解説
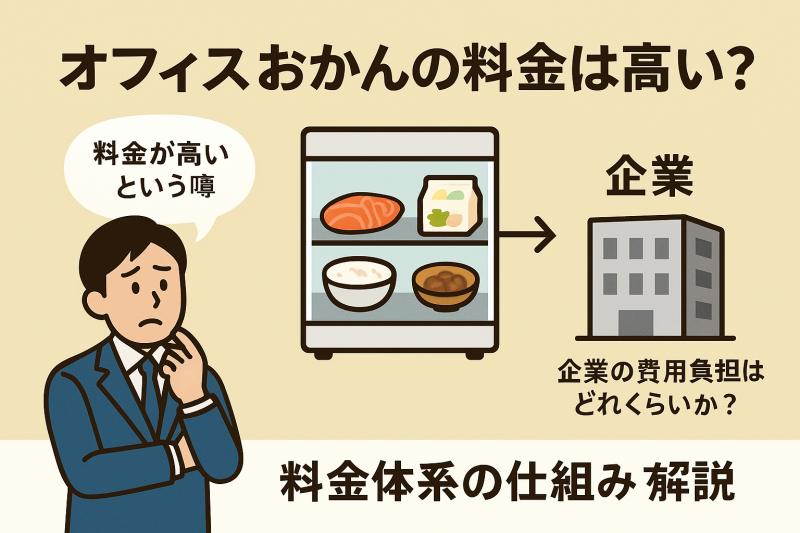
オフィス向上計画・イメージ
まず、オフィスおかんの料金が高いのかを判断するために、企業が支払う月額料金や従業員との負担割合など、料金体系の基本的な仕組みから詳しく見ていきましょう。
企業が支払う月額料金の仕組み
まず、オフィスおかんの料金は、企業側が負担する「サービス・システム利用料金」と、従業員が支払う「商品代金」の2つで構成されています。
そのため、「料金が高い」と感じるかどうかを判断するには、まず企業が支払う月額料金の仕組みを理解することが大切です。
企業が負担する月額料金は、提供されるお惣菜の個数に応じたプランによって変動します。公式サイトでは具体的な金額は「要問い合わせ」となっていますが、一般的に以下の要素が含まれています。
②商品の配送料および納品・管理に関わる費用
③サービスを維持するためのシステム利用料
これらの費用は「月額の固定費」として企業が負担します。例えば、月に60個のお惣菜を納品するプランの場合、サービス・システム利用料金として42,900円(税込)がかかります。
つまり、従業員が商品を購入するかどうかにかかわらず、企業側には毎月一定の固定費が発生する仕組みです。
この固定費を高いと捉えるか、福利厚生への投資として妥当と考えるかが、導入を判断する上での一つの指標となります。
従業員と会社負担の料金内訳

オフィス向上計画・イメージ
従業員が1品100円~という手頃な価格でお惣菜を購入できる背景には、会社側の費用負担が存在します。
料金の内訳を正しく把握することで、サービスの全体像が見えてきます。
会社の負担部分
前述の通り、会社は月額の「サービス・システム利用料金」を負担します。
これに加えて、従業員が支払う100円の商品代金と、実際のお惣菜の原価との差額も、実質的には会社がサービス利用料の一部として負担していると考えられます。
例えば、月に60個納品されるプランで、月額のサービス・システム利用料金が42,900円(税込)の場合、これが会社の直接的な負担額です。
さらに、商品代金として10,800円(税込)(60個×180円で計算した場合の例、詳細は後述)が別途かかりますが、これも企業が支払う料金に含まれているケースが多いです。
従業員の負担部分
従業員は、好きなお惣菜を1品選ぶごとに100円を支払います。
支払い方法は、専用の料金箱への現金投入、または専用アプリ「おかんPay」を利用したキャッシュレス決済(クレジットカード、PayPay、LINEPayなど)に対応しており、利便性が高いのが特徴です。
このように、会社がサービスの基盤となる費用を負担することで、従業員は栄養バランスの取れた食事を非常に安価に利用できるという関係が成り立っています。
したがって、表面的な従業員の支払額だけでなく、会社側の負担額も合わせて評価することが求められます。
オフィスおかんの個人利用は可能か
「オフィスおかん」は、法人向けの福利厚生サービスとして提供されています。そのため、原則として個人が自宅で利用するために契約することはできません。
サービスの根幹は、企業が従業員の働く環境を改善し、健康をサポートすることを目的として費用を負担する点にあります。
専用冷蔵庫の設置や商品の定期配送、在庫管理といった運用フローも、オフィスや事業所といった法人の拠点があることを前提に設計されています。
「オフィスおかん」はあくまで企業と従業員のための「設置型社食」であり、福利厚生の一環として導入されるサービスである、という点を理解しておくことが大切です。
1品100円以外の費用はあるのか

オフィス向上計画・イメージ
従業員が利用する際の基本料金は1品100円ですが、それ以外に従業員側で追加の費用が発生することはありません。
ただし、企業側の視点で見ると、100円という価格設定を維持するために、いくつかの間接的なコストを考慮する必要があります。
まず、企業が支払う月額料金は、選択するプラン(納品されるお惣菜の数)によって変動します。
また、お惣菜を温めるための電子レンジは、基本的に導入企業側で用意する必要があります。
すでに休憩室などに設置されていれば追加費用はかかりませんが、新規に購入する場合はその費用も初期コストとして計算に入れなければなりません。
さらに、一部地域(1都3県の一部を除く)では、商品の受け取りや冷蔵庫への補充、在庫管理などを自社の従業員が行う必要があります。
これは直接的な金銭コストではありませんが、担当者の業務時間を割くことになるため、人件費という観点での「見えないコスト」が発生すると考えられます。
これらの点を踏まえると、従業員にとっては100円で完結しますが、企業側にとっては月額料金以外にも考慮すべき費用や手間が存在することがわかります。
オフィスおかんの料金が高いと感じる要因を検証

料金の基本構造を踏まえた上で、ここでは「値上げ」の噂やメニューの価格、他社比較など、より具体的な視点から「高い」と感じる要因を一つひとつ検証していきます。
オフィスおかんは過去に値上げした?
調べた限りでは、オフィスおかんが料金を値上げした事実はなかったですが、「オフィスおかんの料金が以前より高くなった」と感じる場合、いくつかの要因が考えられます。
まず、サービス提供元である株式会社OKANが、社会情勢や原材料費の高騰などを理由に、企業向けの月額サービス料金を改定している可能性は否定できません。
このご時世ですし、食品をはじめあらゆる物品やサービスの値段が上がってる事実があります。
福利厚生サービスの料金体系も他の例に漏れず、市場環境に応じて見直されることが一般的です。
次に、導入企業側がプランを見直した可能性が考えられます。例えば、これまで契約していたプランよりもお惣菜の納品数が多い、上位のプランに変更した場合、企業の月額負担は増加します。
また、従業員が支払う「1品100円」という価格は、あくまで「想定利用価格」です。
導入企業によっては、福利厚生費の兼ね合いから、従業員負担額を150円や200円に設定しているケースも存在するかもしれません。
以前勤務していた会社と現在の会社で従業員負担額が異なれば、「値上げした」と感じる一因になり得ます。
以上のことから、サービス全体として一律に値上げがあったと断定はできませんが、契約プランの変更や企業ごとの価格設定の違いによって、料金が高いと感じるケースがあると言えます。
100円ではなく180円の商品もある?

オフィス向上計画・イメージ
オフィスおかんの料金体系を考える上で、一部で「180円」という価格についての情報が見られます。これは、企業が支払う商品代金の計算根拠に関わる可能性があります。
前述の通り、従業員は1品100円で購入できますが、これは企業が差額を負担しているからこそ実現できる価格です。
月60個納品のプランでは、企業が支払う料金の内訳に「商品代金 10,800円(税込)」と記載されています。これを60個で割ると、1個あたりの単価は180円になります。
この180円がお惣菜の本来の価格(原価や管理費を含む)であり、企業がこの全額を支払い、従業員からは100円を徴収することで、差額の80円分を企業が補助している、という構造が考えられます。
したがって、従業員が直接180円の商品を目にすることはありませんが、料金体系の裏側では、100円ではない単価が設定されていると推測されます。
この内部的な価格設定が、「オフィスおかんの料金は、見えない部分で高く設定されているのではないか」という印象に繋がる一因かもしれません。
メニューの質と価格は見合っているか
いくら料金が安くても、肝心の料理がおいしくなかったら意味がありません。
オフィスおかんの料金が高いか安いかを判断する上で、提供されるメニューの質は極めて重要です。
その点、オフィスおかんは管理栄養士が監修し、毎月約20種類の新しいメニューが提供される点は、大きな魅力と言えます。
単身者や多忙な従業員が不足しがちな魚や野菜を手軽に摂取できる機会を提供することは、健康経営の観点からも価値が高いと考えられます。
また、お惣菜は冷凍ではなくチルド(冷蔵)であるため、電子レンジでの温め時間が短く済むのも利点です。ですので昼休みなどの限られた時間でも手軽に温かい食事を楽しむことができます。
味付けも、だしを効かせた家庭的な和食が中心で、毎日食べても飽きがこないように工夫されています。
これを「1品100円(従業員負担)」という価格で利用できるのであれば、コストパフォーマンスは非常に高いと言えます。コンビニでおかずを1品追加する場合と比較しても、同等かそれ以上に安価です。
従業員の利用率が低ければ、食事にありつけない従業員一人当たりのコストは割高になります。
メニューの質が高いことは間違いありませんが、その価値を従業員が享受し、会社全体のメリットに繋がるかどうかが、価格の妥当性を測る上でのポイントです。
売れ残りが出た場合の費用負担は

オフィス向上計画・イメージ
設置型社食サービスにおいて、売れ残り(食品ロス)のリスクと費用負担は、企業担当者が最も懸念する点ではないでしょうか?
オフィスおかんの場合、導入時に企業が選択したプランに基づいて、毎月決められた数のお惣菜が納品されます。
企業は、納品されたお惣菜の個数分の料金(サービス・システム利用料金+商品代金)を支払うことになります。
このため、導入時には従業員数やオフィスの利用状況、食事スタイルの傾向などを考慮し、最適なプランを選択することが不可欠です。
現実的に考えたら、まずは様子見な感じで少なめのメニューでスタートし、社員の反応を見つつ、本当に好評ならじょじょに品数を増やしていくという感じでしょうか。
例えば、リモートワークの従業員が多いにもかかわらず、出社率を前提とした過大なプランを契約してしまうと、多くの売れ残りが発生し、費用対効果が著しく低下する恐れがあります。
オフィスおかんでは、導入後の利用状況に応じてプランの見直しや、納品されるメニューのリクエストが可能です。
定期的に利用状況を分析し、売れ残りが出にくい適切なプランに調整していく運用が、コストを最適化する上で重要になります。
他社サービスとの料金比較
オフィスおかんの料金が高いかを客観的に判断するには、他の類似サービスとの比較が有効です。
ここでは、代表的な置き型社食サービスと料金体系を比較してみましょう。
| サービス名 | 初期費用 | 月額料金(企業負担) | 従業員負担額 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| オフィスおかん | 要問い合わせ | 要問い合わせ(プランによる) | 1品100円~ | 管理栄養士監修のチルド惣菜。毎月20種。全国対応。 |
| OFFICE DE YASAI | 要問い合わせ | 49,800円~/月 | 1個100円~ | 新鮮なサラダやフルーツ、無添加惣菜が中心。冷蔵・冷凍プランあり。 |
| オフィスプレミアムフローズン | 0円 | 36,000円~/月 | 1品100円 or 200円 | 冷凍惣菜。化学的合成添加物不使用。月間約160品のメニュー。 |
| ESキッチン | 要問い合わせ | 30,000円~/月(50個プラン) | 1品100円~ | 添加物に配慮した冷蔵惣菜。賞味期限は納品時30日以上。 |
このように比較すると、オフィスおかんの料金体系は業界の標準的な価格帯にあると考えられます。ですので、契約内容によっては他のサービスより高くなる可能性も、安くなる可能性もあります。
例えば、「OFFICE DE YASAI」は野菜やフルーツに強みがあり、「オフィスプレミアムフローズン」は冷凍で長期保存が可能かつメニュー数が豊富です。
以上の点を踏まえると、「オフィスおかんだけが突出して料金が高い」というわけではなく、提供価値と価格のバランスをどう評価するかによって、その印象は変わると言えます。
総評:オフィスおかんの料金は高いのか
この記事を通じて解説してきた内容を基に、「オフィスおかんの料金は高いのか」という問いに対する総評を以下にまとめます。
- オフィスおかんの料金は企業負担の月額料金と従業員負担の商品代金で構成される
- 企業が支払う月額料金はプランによって異なり、公式サイトでは要問い合わせとなっている
- 従業員は1品100円という安価な価格で利用できる
- この低価格は企業がサービス利用料や原価との差額を負担することで実現している
- 料金が高いと感じるかは企業の月額固定費をどう捉えるかによる
- 原則として個人での契約や利用はできない法人向けサービスである
- 企業側には月額料金の他に電子レンジの用意や管理の手間といったコストがかかる
- 料金が値上げしたと感じる場合、企業のプラン変更や価格設定の変更が要因の可能性がある
- 従業員が180円の商品を見ることはないが、企業側の商品単価として設定されている場合がある
- 管理栄養士が監修した毎月20種類のチルド惣菜というメニューの質は高い
- 売れ残りが出た場合の費用は企業負担となるため適切なプラン選択が不可欠
- 他社の置き型社食サービスと比較しても料金が突出して高いわけではない
- 料金は業界の標準的な価格帯にあり、サービス内容とのバランスが重要
- 費用対効果は従業員の利用率や満足度に大きく左右される
- 最終的に料金が高いか安いかは、福利厚生への投資価値をどう判断するかで決まる

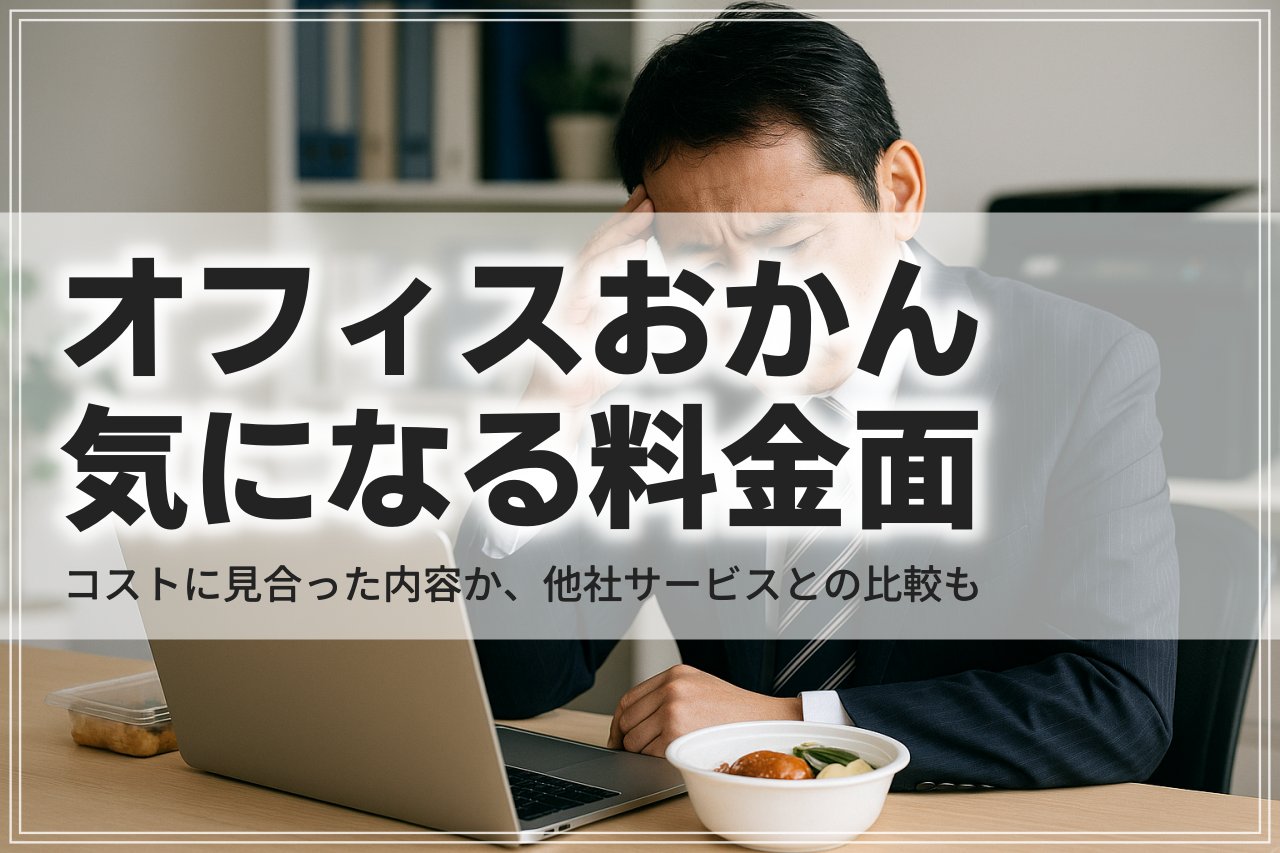


コメント